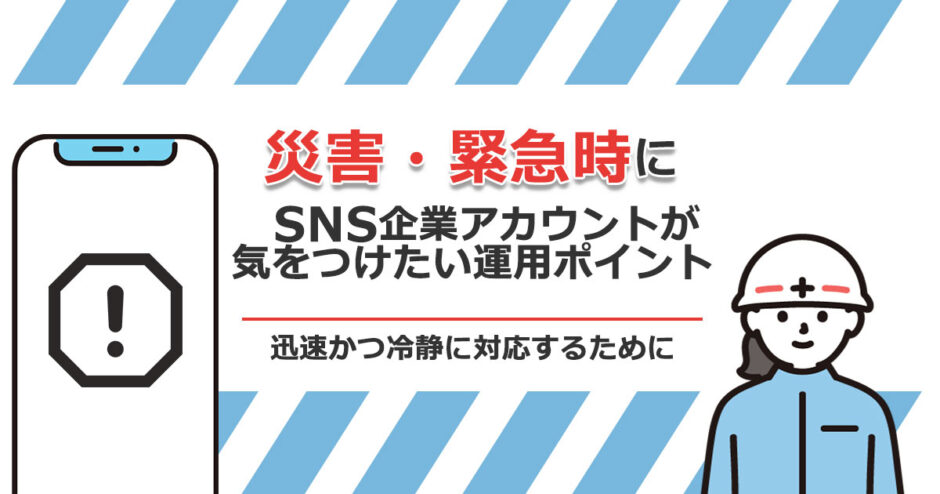地震や台風などの災害、突発的な事故や事件が発生した際、企業のSNSアカウントも慎重な対応が求められます。通常どおりの投稿が不適切と受け取られることもあれば、正確な対応が信頼につながることもあります。
本記事では、企業アカウントの運用を担当されている方に、災害や緊急時にSNSを運用するうえで、どのような対応が求められるのか、実務的な観点から注意すべきポイントを整理してご紹介します。
1.緊急時、SNS企業アカウントが投稿を立ち止まるべき理由。
タイムラインに表示させるべき情報は?!
災害や重大な事故が発生した際、SNSのタイムラインには自治体や交通機関、報道機関など、被災者や関係者にとって重要な情報が多数流れています。こうした状況下で、企業の通常の楽しく面白い投稿が多すぎると、本来必要な情報が埋もれてしまい、結果として多くの人が正確な情報を得られず困惑する恐れがあります。
そのため企業は、緊急時において「タイムラインに何を優先的に表示させるべきか」を意識することが非常に重要です。

通常モードの投稿は「不謹慎」になることも。
一方で、通常通りのキャンペーンの告知や、面白い内容の投稿を続けてしまうと、空気を読めていないということで「不謹慎」と受け取られ、企業の信頼を損なうリスクも高まります。
緊急時こそ、安易に発信を続けるのではなく、この投稿は本当に発信すべきか、自社の投稿がユーザーのタイムラインの優先順位を乱していないかなどを冷静に判断し、立ち止まることが必要です。
2.SNS企業アカウント運用で災害・緊急時にまず確認すべきこと。
何が起きたのか・どのくらいの災害が発生したのか情報を収集する。
企業のSNS担当者は災害や事故が発生した際、まずは信頼性の高い情報を的確に収集することが何より重要です。

情報収集の際は、公式かつ一次情報を重視しましょう。
特に優先して確認すべき情報源としては、気象庁の公式ウェブサイトやSNSアカウント、総務省の災害関連情報ページが挙げられます。これらは政府や公共機関が発信する信頼性の高い情報源であり、最新の災害状況や避難指示、交通情報などが得られます。
また、被災地域の自治体公式サイトやSNS、インフラ企業(電力・ガス・通信など)の公式発信も重要な情報源です。地域の状況や事業への影響を把握するために、複数の信頼できる情報をクロスチェックすることが望まれます。
■気象庁公式
Webサイト
X(旧 Twitter)「気象庁防災情報」
■総務省消防庁
Webサイト
■NHK 生活・災害情報
Webサイト「NHK NEWS WEB|気象・災害ニュース一覧」
X(旧 Twitter)「NHK生活・防災」
■電力、ガス、通信などインフラ企業の公式情報など
3.SNS企業アカウントの運用担当者が忘れがちな対応。
緊急時の対応で見落とされがちなのが、普段どおりの運用への目配りです。特に、事前に設定されたSNSの投稿スケジュールなどに注意が必要です。

まず確認したいのが、予約済みの投稿やSNSキャンペーンのスケジュールです。
災害発生時に通常通りの内容がタイムラインに流れると、状況にそぐわない印象を与えてしまい、企業への信頼を損なうことにつながりかねません。
すぐに投稿予定を確認し、一時停止や削除の対応を行いましょう。また、「一時的に運用を止めます」といった宣言投稿は、かえって不要な情報になる可能性があるため、いったん運用を止めることが望ましい判断です。
通常の投稿だけでなく、ユーザーとの交流も一時停止するのが望ましい対応です。
アクティブサポート(リプライやコメントへの返信)、リポスト、「いいね」などのリアクションも、状況によっては不適切と受け取られる可能性があります。
自動配信で回っているSNS広告が、災害発生時にも変わらず表示され続けてしまうケースがあります。
被災時のタイムラインの文脈から浮いてしまうSNS広告は、ユーザーに違和感や不快感を与える可能性があるため、広告配信の一時停止や内容の見直しも併せて検討しましょう。
このように、緊急時は「発信しない対応」も重要な判断のひとつです。日頃から運用の自動化が進んでいる状態であるほど、止めるべき投稿のチェックリストを持っておくと安心です。
- 予約投稿の一覧を確認し、不要・不適切なものは一時停止または削除。
- 定期投稿のスケジュールを一時停止。内容や表現がそぐわないものは変更する。
- SNSキャンペーンや販促投稿の実施有無を確認・該当部署への共有。
- SNS広告の出稿状況を確認し、一時停止またはターゲティング・内容の見直し。

アクティブサポート・コミュニケション
SNS上に一般ユーザーから投稿されている貴社商材(サービスや商品)についての投稿へ、企業アカウント(公式アカウント)から能動的にアプローチするSNS施策を、アディッシュプラスがサポートさせて頂きます。
4.平時から備えておくべき緊急時の運用ルール。
災害や事故といった緊急事態は、いつ起こるか分かりません。だからこそ、通常時からの備えが、企業アカウントの信頼性と対応スピードを大きく左右するといえます。
社内広報や危機管理チームとの連携、連絡フローの確認。
まず重要なのは、社内での連携体制の整備です。広報部門だけでなく、危機管理や総務、カスタマーサポートなど関係部署と連携し、万一の際にどのような情報を共有し、どう判断するかという流れを明確にしておきましょう。
緊急連絡先や判断フローを社内で共有しておくことで、迅速な初動対応につながります
どのレベルで、どのような投稿を止めるか。
次に考えておきたいのが「どのレベルの事態で、どの範囲の投稿を止めるか」の基準です。
たとえば、地震によっては被害が少ない場合があります。そのため状況に応じた運用判断の線引きを、あらかじめ社内で擦り合わせておくと安心です。
SNS投稿の再開はいつか。
被災地の状況や社会全体の空気感をふまえ、SNS投稿の再開時期の判断をしましょう。再開の際は、まずお見舞いや営業状況の案内など、配慮を伴う投稿から始めることが望まれます。
再開の判断にあたっては、社会情勢の把握が欠かせません。例えば、X(旧 Twitter)のトレンドに明るい話題が上がってきた時、テレビではNHKの緊急事態の字幕の表示がなくなった時など、上段と同様に信頼性の高いメディアや情報源を参考にしながら、自社にとって適切な再開タイミングを見極めましょう。
どの情報を優先的に確認するか、社内であらかじめ共有し、この情報が更新され次第、次のアクションの判断に進むというルールを設けておくと、スムーズな再開につながります。
5.緊急時の対応マニュアルを準備しましょう。
ここまでご紹介した内容をもとに、自社の状況を確認したら、緊急時に即座に対応できるよう「対応マニュアル」としてまとめておくことをおすすめします。
SNS投稿の一時停止や、その判断基準を明文化しておくことはもちろん、深夜・休日でも必要な連絡が取れる体制づくりも欠かせません。
また、SNS担当者が1人しかいない場合や外部に運用代行を委託している場合は、誰がどの段階で最終判断を下すのかなどを事前に明確にしておきましょう。
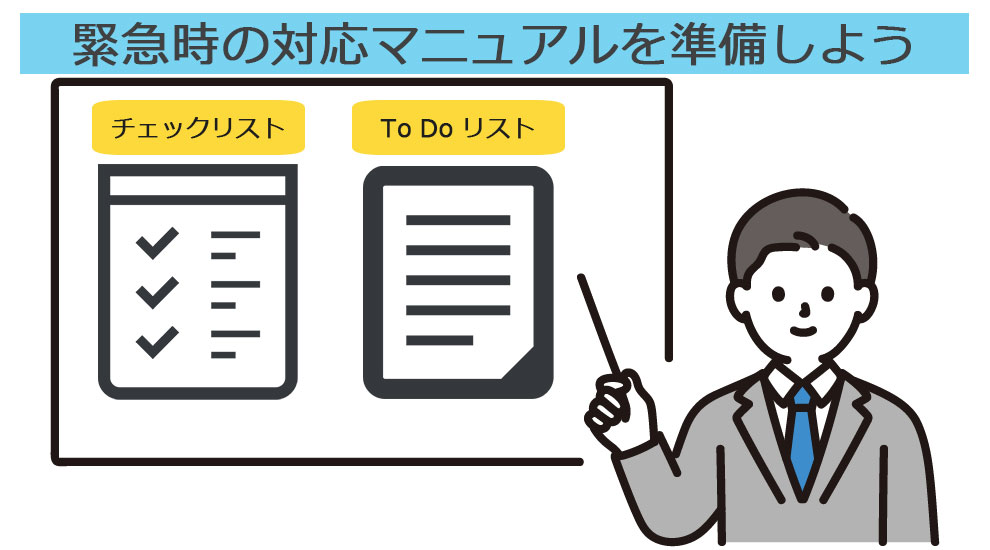
連絡体制
- 広報・危機管理・総務など関係部署との連携体制。
- 深夜・休日に判断できる担当者・連絡先の明確化。
- SNS運用を委託している場合、対応ルールを伝達し、外部と連携体制。
運用レベル
- 「どの状況で投稿を止めるか」の判断基準を定める。
- SNSの投稿停止だけでなく、リプライや「いいね」などのアクティブサポートも含めて一時中断する基準を設ける。
- キャンペーンや広告出稿を一時停止・見直しする際の運用フローを整理しておく。
このような備えがあることで、いざという時に何をどうするかで迷う時間を最小限に抑えられ、企業アカウントの信頼を守る第一歩となります。
6.事業に影響が出る場合。
緊急時、災害や事象によって、自社に直接影響がある場合は、WebサイトやSNSからサービスや事業の状況について公式情報を正確に届ける責任も生じます。
自社への影響有無の初期確認。
災害が自社の事業や拠点、従業員に与える影響の有無を初期段階で確認することも重要です。例えば、自社施設の被災状況や従業員の安否、物流やサービス提供への影響などを把握し、状況に応じた情報の公開が求められます。
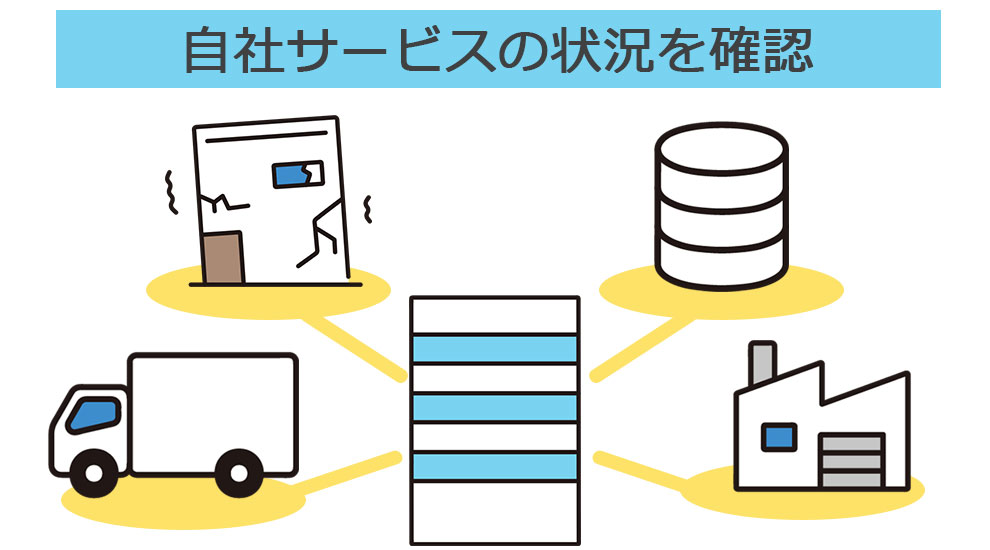
事業そのものに影響が出るケース。
たとえば商品の出荷停止、配送遅延、サービス提供の一時中断などがある場合には、WebサイトやSNSでタイムリーにお知らせを行うことが求められます。こうした発信は、問い合わせの急増や誤解の拡大を防ぐうえでも効果的です。
自社の状況把握
- 被災地に自社の拠点や関係先があるか?
- 顧客へのサービス・商品提供に支障が出ていないか?
- 営業状況や対応方針について、顧客に伝えるべき情報はあるか?
投稿内容の準備
- 広報・危機管理・総務など関係部署と連携し、サービスについての公開する情報を確認する。(サービス再開時期・遅延状況の確認など)
- 利用者にサービスの対応・利用期限のあるサービスの救済措置を伝える場合、配慮のある表現になっているか?
まとめ:災害・緊急時、タイムラインの優先は何かを考えよう。
災害時は「発信すること」よりも「沈黙する勇気」と「判断のスピード」が重要。
災害や事故が発生した際、企業アカウントにとって最も重要なのは、「この状況で本当に発信すべきか」を冷静に判断することです。状況が明確になるまで、いったんは運用を停止することをおすすめします。
普段通りの投稿やSNSキャンペーンが、思わぬ誤解や批判につながってしまうこともあります。日々の丁寧な運用で築いたフォロワーとの関係が、一つの投稿で損なわれることもありますので注意が必要です。
緊急時の運用方針を策定しましょう。
また、今回ご紹介したような確認ポイントや初動対応の流れは、日ごろから緊急時対応マニュアルとして整備し、SNS運用担当者同士で共有しておくことをおすすめします。誰が対応しても一定の判断と行動が取れるようにしておくことが、自社アカウントの安定した運用につながります。
いざという時にも落ち着いて判断できるよう、平時からの準備とチーム内での共有を大切にしていきたいと弊社でも思っております。
本記事が、緊急時におけるSNS運用の見直しや備えの一助となれば幸いです。

アディッシュプラスのSNS運用代行
主要SNSであるX(旧Twitter)、Instagram、Facebookのビジネスアカウントの運用をサポートいたします。開設から運用代行までをワンストップで代行しております。各SNSの特徴を活かした投稿コンテンツの提案を行い、貴社のブランディング向上の後押しをいたします。
お気軽にお問い合わせください。
SNS運用やSNSキャンペーン事務局支援サービスについて、ご相談やお見積りなどのご質問がある方は、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。